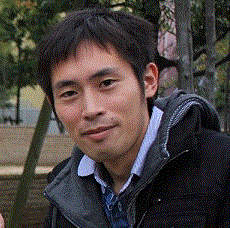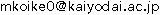|
ホームページ |
|
メールアドレス |
|
|
関連リンク |
|
|
小池 雅和 (コイケ マサカズ) KOIKE MASAKAZU
|
論文 【 表示 / 非表示 】
-
Optimal Scheduling of Storage Batteries and Power Generators Based on Interval Prediction of Photovoltaics -- Monotonicity Analysis for State of Charge --
Masakazu Koike, Takayuki Ishizaki, Nacim Ramdani, Jun-ichi Imura , 2020年01月
IEEE Control Systems Letters , 4 (1) , 49 - 54
-
Optimal Scheduling of Storage Batteries and Thermal Power Plants for Supply-Demand Balance
Masakazu Koike, Takayuki Ishizaki, Nacim Ramdani, Jun-ichi Imura , 2018年08月
Control Engineering Practice , 77 , 213 - 224
-
Monotonicity Analysis of Day-Ahead Multi-Storage Thermal Scheduling under PV Interval Uncertainty
Tsuru Tsutsumi, Masakazu Koike, Nacim Ramdani, Takayuki Ishizaki , 2025年09月
Proc. of SICE Annual Conference
-
Modification of control of synchronization of cluster atomic clocks and control of anchoring to standard time during changes in network structure
Yuga Kojima, Masakazu Koike, Gakuto Kobayashi , 2025年09月
Proc. of SICE Annual Conference 2025, (ポスター)
-
Event Trigger Control for Anchoring of Cluster Atomic Clocks to the Standard Time System by GNSS Receiver
Yuga Kojima, Masakazu Koike, Takayuki Ishizaki, Takahiro Kawaguchi, Yuichiro Yano, Yuko Hanado, Yosuke Kurata , 2025年09月
Proc. of SICE Annual Conference 2025
著書 【 表示 / 非表示 】
-
次世代電力システム設計論 再生可能エネルギーを活かす予測と制御の調和
井村順一, 原辰次, 東俊一, 石崎孝幸, 井上正樹, 小池雅和, 他28名 , 2019年11月
株式会社オーム社 , P135-142
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
研究期間: 2021年04月 - 2025年03月 代表者: 千田 有一
基盤研究(B) 研究分担者 23K20945
本研究では,操作量が離散値に制約される離散値駆動型アクチュエータ系の制御方法(離散値制御)の確立に取り組む。より具体的には,実用化の課題である,操作量の切り替え頻度の低減化と性能向上のトレードオフ問題への簡便なアプローチ方法の構築,およびサーボ問題における定常状態でのチャタリング的な入力切り替えの回避,車両の任意経路追従性能向上やパルス駆動に起因した機械振動励振の回避に取り組む。これにより,各種課題を解決した離散値制御系の設計方法を確立する。
-
研究期間: 2020年04月 - 2023年03月 代表者: 小池 雅和
若手研究 研究代表者 20K14711
太陽光発電(PV)の不確かさを適切に考慮しながら,前日に供給者側のリソース(火力機と蓄電池)の最適な運用計画を立てる問題に着目する.特徴はPVと需要の予測が信頼区間(幅)として与えられている点である.信頼区間内の無数のプロファイルに対応する無数の最適運用計画プロファイルが存在する.その運用計画の取り得る領域(幅)が事前にわかれば最適リソース運用が実現できる.厳密な幅を求めるためには厄介な最適化問題を解く必要があり,これは解の単調性が保存される問題でなければ現段階では解く事ができない.そこで,どういった問題(制約条件や目的関数など)なら単調性が保存されているのかを解析する手法を開発する.
-
深海用ソフトロボティクスの実現へ向けて -非線形同期制御を使った人工筋肉の研究-
研究期間: 2018年04月 - 2021年03月 代表者: 田原 淳一郎
基盤研究(C) 研究分担者 18K04577
本年度はコロナの影響もあり、非線形同期を使ったシミュレーションを中心に研究を行った。特に、柔軟な構造物を構成するためには分岐を伴った非線形振動子の構成が重要になるため、これらについて研究調査を行った。また、振動子の情報をアナログ連続情報からデジタルパルスに変更する事により、外乱に対してロバストになることが分かった。これは、今後、実験を行う際に重要になると考えられる。本研究において、水中での信号伝達にLEDと光ファイバを利用する予定であったが、海外製のコネクタ等の購入ができなかったため他の手法を検討した。
非線形同期回路についてはLEDとフォトカプラを用いて作成する事が可能となった。
非線形同期のシミュレーションについてはMatlabとPythonを用いて行った。Matlabを使う事により、多様なシミュレーションが可能になった。
また、昨年度購入した3Dプリンターを用いて空気室を作成し、アクチュエータの設計を行った。水中での試験を考えると光での通信を考える必要があるため、光によるパルスとVDPを使った非線形同期回路等を作成した。この回路を基本として人工筋肉を動作させる。
特にVDPを複数結合しても、同位相の同期と逆位相の同期が実現可能となったため、多様な運動が実現できる事も理解できた。特に同位相・逆位相が制御可能となると、ベクトル演算により多様な動作が可能になる。今後は周期を変更する手法についても検討を行う。
これらの得られた知見を元に人工筋肉群を制御する事も視野に入れる。
コロナの影響で海外製の部品が購入できなくなるなど、実験に関しては相当な遅延が発生すると思われたため、シミュレーションを中心に研究を行った。実験は遅れたがシミュレーションに関しては十分な時間がとれた。
昨年度に先行して実施した、分岐を伴った非線形振動子とパルスによる情報交換を使ったVDPのシミュレーション結果を用いて、空気室を持ったアクチュエータを作成し、非線形同期手法であるLIFやVDPを使った制御が可能であることを示す。
特に水中での試験を考えており、海外製のコネクタを使わずとも試験を可能にする。また空気室を構成する際のアルゴリズムとしては、粘菌の様に利用頻度の高い部分と低い部分を組み合わせることにより、成長や構成を変える手法を検討する必要性がある。
また、非線形同期で制御する柔軟な構造物には見えない遅れがあり、これが制御を困難にするため、これについても調査を行う。
特に、空気室を持った柔軟構造体を構成する手法については研究の余地が多く、知見が少ないため文献調査等を行う。一方で電子制御回路等については先行している。 -
研究期間: 2016年04月 - 2019年03月 代表者: 小池 雅和
若手研究(B) 研究代表者 16K18318
平成29年度は水槽全体加振を前提とした基礎実験と数値モデルの構築をおこなった.その結果,従来文献で提案されている粒子の収束位置と振動数の関係式の適用範囲を明らかにし,あらなた関係式を導出した.以下詳しく報告する.
【水槽全体加振を前提とし,水中搬送での基礎研究】加振周波数をシーケンシャルに組み合わせることで,特定の位置ではなく任意の位置に水中粒子を移動させる基礎実験をおこなった.その結果,多数の粒子を任意の位置に移動させるのは非常に困難であることがわかった.低い振動数であれば,綺麗に特定の位置に搬送できるのだが,高い周波数だと,振幅を大きくできないため,搬送力が低下してしまうのが大きな原因である.また,容器の壁面と振動方向を厳密に直交した位置関係で保つ必要があり,その調整誤差も原因の一つである.また,使用した粒子の材質はAS樹脂,ガラス,ジルコニアであるが,AS樹脂が搬送させやすいことも分かった.
【数値モデルの構築】従来文献による粒子の収束位置と振動数の関係式では現象を厳密には表現できないことがわかった.特に,粒子の直径が大きい場合には誤差が大きくなる.そこで,新たに,従来文献の関係式を修正し,実現象を表現できる関係式を導出した.実現象をより厳密に表現できる関係式を導いた点が本年度の大きな貢献である.
【局所振動を前提とし,水中搬送での基礎研究】振動発生装置の選定と装置設計をおこなった.材料購入と装置組み立ては未完了である.空気ばねを用いた効率的な振動発生手法に関しては第22回知能メカトロニクスワークショップ,第60回自動制御連合講演会にて発表した.また電気学会に論文投稿中である.
平成29年度は予定の研究よりも基礎的な研究にとどまった.予定では局所振動を前提とした水中搬送での基礎実験まで進める予定だったが,この実験は未完了である.その原因は数値モデルの構築や水槽全体加振型装置のトレー形状の見直しに思った以上に時間を要したためである.
平成29年度は予定の研究よりも基礎的な研究にとどまった.そこで,本年度は昨年度実施予定であった局所振動を前提とた水中搬送基礎実験を完了させる.そのため,研究計画を以下のように変更する.
<BR>
【振動発生装置の部集と組立て・調整】(平成30年4月~7月)
二本の振動発生装置(パルスモータ式)と1000mm×500mmの容器を用いた実験装置を組み立てる.その後,所望のサイン波の動きで動作させるために,必要パルスの時系列データを作成し,動作確認を行う.
<BR>
【局所振動を前提とし,水中搬送での基礎実験】(平成30年8月~)この期間はブイ型振動発生装置による粒子の移動現象を確認する予定である.具体的には,水槽全体加振と同様の現象を引き起こす振動パターンを探る.この基礎実験では推進,粒子,振動数など,多数のパラメータを変えた実験が必要になるため,曳航水槽を用いた大規模な実験は実施しない予定である.
授業科目 【 表示 / 非表示 】
-
担当授業(学部)
制御工学Ⅰ
-
制御工学Ⅱ
-
応用制御工学
-
短艇実習
-
舶用工業実務論
-
電子機械工学ゼミナール
-
電子機械工学入門
-
電子機械工学実習
-
電子機械工学実験
-
担当授業(大学院)
オートマティクス実験
-
情報制御工学
-
海洋サイバネティクス特別演習
-
海洋サイバネティクス特別研究
-
海洋システム制御実験
-
海洋システム制御工学