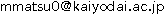|
ホームページ |
|
https://sites.google.com/view/fishpathology-lab/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 |
|
メールアドレス |
|
|
関連リンク |
|
|
松本 萌 (マツモト メグミ) MATSUMOTO Megumi
|
論文 【 表示 / 非表示 】
-
Attenuation mechanisms of the P7-P8 live-attenuated cyvirus cyprinidallo2 vaccine potentially involve apoptosis non-inhibition feature: insights into virus pathogenesis
Hiroaki Saito, Yuki Midorikawa, Takumi Okamura, Samuel Mwakisha Mwamburi, Shungo Minami, Manami Yuguchi, Hidehiro Kondo, Megumi Matsumoto, Goshi Kato and Motohiko Sano , 2026年02月
Journal of general virology , 107 (2)
-
Development of an effective DNA vaccine against viral edema of carp/koi sleepy disease caused by carp edema virus
Rintaro Ogawa, Shuntaro Baba, Momo Hotta, Kobayashi Kenichiro, Tatsuya Kishihara, Hisato Matoyama, Shoh Sato. Megumi Matsumoto, Goshi Kato, Motohiko Sano. , 2026年01月
Journal of fish diseases
-
Development of DNA vaccines against Mycolicibacterium cyprinidarum isolated from diseased koi carp
Goshi Kato, Kentaro Motoyama, Megumi Matsumoto, Motohiko Sano. , 2025年12月
Fish Pathology , 60 (4) , 203 - 206
-
Development of an effective DNA vaccine against ayu atypical cellular gill disease using draft genome information of the causative agent, Plecoglossus altivelis poxvirus
Shuntaro Baba, Tomoki Koyama, Daiki Komatsu, Tsubasa Uchino, Yuki Midorikawa, Yasunori Takano, Tatsuya Mori, Yuya Takagi, Shinpei Wada, Hidehiro Kondo, Megumi Matsumoto, Goshi Kato, Motohiko Sano , 2025年08月
Virology , 110671 - 110671
-
Cell-mediated and humoral immune response of cyprinids induced by a live attenuated vaccine against cyprinid herpesvirus 2 infection in comparison to the virus non-permissive high temperature water treatment
Hiroaki Saito, Lik-Ming Lau, Shungo Minami, Manami Yuguchi, Megumi Matsumoto, Teruyuki Nakanishi, Hidehiro Kondo, Goshi Kato, Motohiko Sano , 2024年10月
Fish and Shellfish Immunology , 154
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
魚類ウイルス病の生簀内再発を予測する数理モデル確立に向けた基盤研究
研究期間: 2025年04月 - 2028年03月 代表者: 松本 萌
若手研究 研究代表者 25K18299
養殖魚に発生するウイルス疾病は、ワクチンや薬剤を用いた治療が困難であり、毎年多くの魚種で被害が報告されている。特に近年では、見かけ上健康であるが魚体内にウイルスを保持している「無症候性親魚キャリア」による年越しの疾病再発・拡散が徐々に顕著化しており、発症前の予防が非常に重要である。ところが、キャリア個体は見かけから特定することができないため、未然の予防が難しい。本課題では、このような外見からでは判断できない無症候性親魚キャリアによる生簀単位での疾病再発を予測する数理モデルの確立を目指す。その基盤研究として、本研究では生簀中のキャリアの存在を疫学的に調査し、「群」としての発生動向を追う。
-
研究期間: 2024年07月 - 2026年03月 代表者: 松本萌
研究活動スタート支援 研究代表者 24K23143
養殖魚に発生する魚病は、養殖事業に甚大な経済的被害をもたらしている。国内で広く利用されている不活化ワクチンは一部の細胞内寄生細菌やウイルスに対する効果が弱いことから、新たなワクチン開発が喫緊の課題である。申請者はこれまでの研究で、病原体由来の「脂質」が、魚類の免疫応答を強く活性化することを明らかにした。さらに、脂質分子を結合可能な魚類特有の非古典的MHCクラスI分子「L系統」が、Bリンパ球に発現していることを発見した。本研究では、申請者らが発見したL系統陽性Bリンパ球の特徴を明らかにし、魚類が独自に展開している免疫応答の中核を担っているのは、自然リンパ球であるのかを明らかにする。
-
研究期間: 2023年04月 - 2028年03月 代表者: 佐野 元彦
基盤研究(A) 研究分担者 23H00343
魚類ウイルス病において持続感染した感染耐過魚は新たな感染源となるため、その制御が必要である。そこで、強毒化が問題となっているサケ科魚類の伝染性造血器壊死症(IHN)をモデルとし、①ウイルスの持続感染がどのように起こるのか、その成立条件は何か、②持続感染状態がどのようにウイルス変異・強毒化をもたらすのか、③免疫機能のどのような因子の活性化が持続感染の発生抑制に有効か、④持続感染の発生抑制効果があるワクチンはどのようなものか、を明らかにする。以上から、持続感染を制御する新たなワクチンプログラムの活用により魚類養殖におけるウイルス感染環を総合的に制御する、新たな魚病対策を提起する。
-
水温変化が引き起こす魚類ミコバクテリア症の再燃メカニズムを探る
研究期間: 2020年04月 - 2023年03月 代表者: 松本 萌
若手研究 研究代表者 20K15596
養殖魚に発生する魚類ミコバクテリア症は、多大な経済的被害をもたらしているにも関わらず未だワクチンも治療薬も開発されていない極めて厄介な疾病である。本疾病の最大の特徴は、初期の感染後「休眠期」と呼ばれる潜伏期間を経て再発に至る「内因性再燃」であるが、この再燃に対する防除策はこれまでに確立されていない。申請者はこれまでの研究から、休眠菌には見られない菌体の脂質層が再燃に関与していることを明らかにし、その脂質層の状態変化には水温が関与していることを見出した。そこで本研究では「外水温と菌体脂質層の組成変化の関係性」を切り口に本疾病の再燃メカニズムを明らかにし、再発の防除を試みる。
養殖魚に発生する抗酸菌症は、日本の養殖業に多大な経済的被害をもたらす疾病の一つである。原因細菌であるMycobacterium spp.は、感染後すぐに症状を示す「活動期」と、宿主細胞にとどまり再燃の機会を待つ「休眠期」の2つの状態を持つ。
これまでの研究において、ニジマス抗酸菌症の原因細菌であるMycobacteroides salmoniphilumが、in vitroの低温培養(5℃)で休眠することが明らかとなっており、さらに、5℃で飼育したニジマス体内でもM. salmoniphilumは休眠することが明らかとなった。一方で、M. salmoniphilumの休眠菌に対してニジマスは免疫応答を示さなかった。本年度は、休眠菌に対してニジマスが免疫応答を誘導しなかった原因を明らかにするため、休眠菌及び活動菌の生物学的および生化学的な特徴付けを行った。 -
脂質抗原に対する魚類の細胞性免疫誘導機構の解明と新規水産用ワクチン開発への挑戦
研究期間: 2019年04月 - 2022年03月 代表者: 松本 萌
特別研究員奨励費 研究代表者 19J01830
これまでの研究により、IL-12を魚体内で産生できれば、細胞内寄生細菌感染症を予防できる可能性が示されている。さらに細胞内寄生細菌由来の糖脂質成分が本疾病のワクチンアジュバントとして使用可能であることが分かっている。しかし、これら糖脂質がどのように魚体の免疫応答を活性化させているのかは不明である。
糖脂質および菌体由来の脂質を特異的に認識するCD1ファミリー分子は、魚類では相同遺伝子が見つかっていないものの、アロタイプが少なく糖脂質の結合に適した構造を持つMHC様分子の存在が示唆されている。そこで、この新奇MHC分子が糖脂質抗原に対する免疫の誘導に関与するのではないかと考えた。
魚類の細胞内寄生性細菌感染症は養殖場において最も問題になっている感染症であり、その多くにおいて効果的な防除法が未だ確立されていない。特に、多くの魚種に共通して発生する抗酸菌症の原因細菌であるMycobacterium属細菌は、菌体の最外周部に豊富な脂質層を有しており、これが宿主に対し高い病原性を示す。ほ乳類では、このような脂質抗原に対する免疫応答において非古典的MHCクラスI分子である「CD1」が中心となり、抗原を排除することが知られている。一方魚類では、ほ乳類のCD1に相当する分子がゲノム上に存在しないが、非古典的MHCクラスI分子である「L系統」がCD1に相当する機能を持つことが予想されている。そこで本研究では、L系統を介した細胞内寄生細菌の脂質に対する魚類独自の免疫応答を明らかにすることを目的とした。
本研究の対象生物であるニジマスはゲノム上に2種類のL系統分子LAA遺伝子およびLBA遺伝子を持つ。そこで、脂質抗原として知られる、ニジマス抗酸菌症原因細菌Mycobacteoides salmoniphilum由来のミコール酸をニジマスに接種し、14日後、28日後のLAAおよびLBAの遺伝子発現を調べたところ、ミコール酸刺激に対しLBA遺伝子の発現が優位に上昇することが明らかとなった。また、LBA抗原に対するモノクローナル抗体を作製し、LBA発現細胞を調べたところ、マクロファージ等の抗原提示細胞に発現していることが明らかとなった。このとから、脂質抗原はLBA分子によって提示されている可能性があることが示唆された。
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。