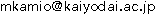|
メールアドレス |
|
|
関連リンク |
|
|
神尾 道也 (カミオ ミチヤ) KAMIO MICHIYA
|
論文 【 表示 / 非表示 】
-
The smell of Panulirus argus virus 1 (PaV1) infection: Disease-induced changes in metabolites in urine and hemolymph of Caribbean spiny lobsters Panulirus argus
Boyu Qin, Donald Behringer, Abigail K. Scro, Erica Ross, Hajime Uchida, Satoshi Yoshimura, Jan Tebben, Tilmann Harder, Charles Derby, Michiya Kamio , 2026年02月
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY , 214
-
Chemical cues for intraspecific chemical communication and interspecific interactions in aquatic environments: applications for fisheries and aquaculture
Michiya Kamio, Hidenobu Yambe, Nobuhiro Fusetani , 2021年11月
Fisheries Science , online first
-
Morphological and behavioral indicators of reproductive premolt females of the helmet crab Telmessus cheiragonus
Michiya Kamio, Hiroki Osada, Hirona Yano , 2021年05月
FISHERIES SCIENCE , 87 (3) , 331 - 337
-
Hemolytic compound 3,7,11,15-tetramethyl-hexadecan-1,19-disulfate found in the invasive European sea squirt Ascidiella aspersa
Hiroshi Nagai, Shuya Shibahara, Ryoji Matsushima, Hajime Uchida, Makoto Kanamori, Yasuyuki Nogata, Michiya Kamio , 2021年01月
FISHERIES SCIENCE , 87 (1) , 145 - 150
-
記録的猛暑の2023年に北海道函館市臼尻町沖で採集されたイセエビ型稚エビの形態及び遺伝学的種特定
神尾 道也, 佐々木 彩花, 佐々木 潤, 柳本 卓, 張 成年 , 2025年06月
水生動物 , 2025 (0) , AA2025-24
著書 【 表示 / 非表示 】
-
Chemical Communication in Crustaceans, T. Breithaupt and M. Thiel (eds.)
神尾道也 , 2011年
Springer Science+Business Media , Approaches to a molecular identification of sex pheromones in blue crabs, Pp. 393-412 , 0-0
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
大型甲殻類が分泌する水中硬化型充填接着剤【交尾栓】の分子構造および凝固機構の解明
研究期間: 2025年06月 - 2028年03月 代表者: 神尾 道也
挑戦的研究(萌芽) 研究代表者 25K22386
クリガニのオスは射精物を強固な「水中硬化型充填剤(交尾栓)」として凝固させ、メスの生殖孔を塞ぎ、自分の精子の受精を確実なものとする。交尾栓は新規水中硬化型充填剤への応用の可能性を持つが、構成分子の構造および射精物が水中で凝固する機構は未解明である。クリガニの交尾栓はタンパク質であるため、本研究では交尾栓構成タンパク質の化学構造と凝固機構を解明する。タンパク質性の交尾栓が海水中で硬化する仕組みの解明は、生分解性を備えた環境にやさしい、新規水中硬化型充填接着剤開発への社会実装につながり、交尾栓タンパク質の遺伝子塩基配列の解明は、甲殻類全体の新たな進化生物学研究分野に発展する萌芽性を持つ。
-
甲殻類幼生の天然餌料に含まれる摂餌促進物質の探索とそれを用いた高嗜好性飼料の開発
研究期間: 2023年04月 - 2028年03月 代表者: 若林 香織
基盤研究(B) 研究分担者 23K26985
匂いや味を感じる化学感覚は、動物が異物を餌と認識し栄養を摂取するための行動を誘起するのに重要な生命システムの一つである。この性質を利用して、甲殻類成体を含む多くの動物で摂餌行動を化学的に誘起する配合飼料が開発されている。一方、甲殻類幼生では、嗜好する匂いや味が十分に調べられていない。本研究では、甲殻類幼生が天然で専食する餌に彼らが嗜好する匂いや味がある、という仮説を立て、天然餌料に含まれる化合物を網羅的に解析し、それらの摂餌促進効果をバイオアッセイにより評価する。さらに、解明される摂餌促進物質を飼料に添加し、幼生の摂餌率を向上する高嗜好性飼料を開発する。
-
甲殻類の繁殖行動を制御する分子基盤:フェロモンとその機能の多様性の解明
研究期間: 2023年04月 - 2027年03月 代表者: 神尾 道也
基盤研究(B) 研究代表者 23K27002
甲殻類が性フェロモンを用いて交信することは知られているが、一言で性フェロモンと言っても、その役割は様々であり、求愛と交尾の合図に加え、配偶者の質(卵の量等)を測る目安、他個体の性転換を抑えて社会構造を安定化させる抑制剤、などが考えられている。本課題はこれらの役割を検証し、フェロモンがどのような物質群なのか、そしてそれらが作られる過程も明らかにする。研究結果は選択的捕獲によるエビ・カニを含む水産資源資源管理や水産養殖の効率化への基礎的な知見を提供する。
-
海産動物の共生・寄生関係の実態と進化・維持機構を「認知進化生態学」で紐解く
研究期間: 2022年04月 - 2025年03月 代表者: 安房田 智司
基盤研究(B) 研究分担者 23K23966
海産動物では多様な共生/寄生関係が知られるが、これらの関係は、単純な生得的・反射的行動で維持されると長年考えられてきた。本研究では、「魚類や甲殻類が高度な認知能力を持つ」という新たな「認知進化生態学(行動・進化生態学と比較認知科学の融合)」の視点から、エビ-ハゼとクマノミ-イソギンチャクの相利共生、ウニ-カニの寄生を対象とし、共生/寄生の実態と維持機構、異種間の情報伝達機構を野外観察や水槽実験、生化学分析により解明する。本研究の成果は、海産動物の共生/寄生の理解に貢献するだけでなく、動物全体の「賢さ」の見直しにも繋がる重要な課題である。
本研究では、(1)テッポウエビ-ハゼ、(2)クマノミ-イソギンチャクを相利共生系のモデル、(3)カニ-ウニを寄生系のモデルとし、野外調査、水槽実験、生化学分析などの手法を用いて、認知進化生態学の視点から研究を実施し、共生の実態と維持機構、異種間の情報伝達機構を解明することを目的とする。
(1)テッポウエビとハゼの相利共生関係は多様で、義務的共生種もいれば、希薄な繋がりの日和見的共生種もいるが、なぜ多様なのかは不明であった。しかし、私たちのこれまでの研究で、餌の乏しい環境では、餌で繋がる義務的共生関係を築くと分かった。そこで、共生関係の繋がりの強さが環境中の餌量で決まるという仮説(餌量仮説)を立て、2022年度は異なる餌環境でエビ4種ハゼ7種の行動を比較し、相利共生の繋がりの強さと環境との関係を調べた。舞鶴や西表島、愛南町での野外調査の結果、エビとハゼの共生関係の繋がりの強さが環境中の餌量の違いによって決まることが初めて示された。この他、水中録音を行った結果、テッポウエビが鉗脚(はさみ)を使って出す音、ハゼが出す音声は、同種同性個体に利用すること分かった。一方、種間のコミュニケーションは音を使ってやり取りしているわけではないことが明らかになった。
(2)クマノミの宿主イソギンチャクに対する給餌行動の実態と種間関係に与える影響を明らかにするため、野外調査を実施した。クマノミはイソギンチャクの食性とクマノミ自身の状態に合わせて、積極的かつ状況依存的に宿主に給餌を行うことが明らかとなった。また、クマノミの宿主イソギンチャクへの給餌が、宿主の成長量を増大させることが分かった。現在、論文の投稿を準備中である。
(3)ゼブラガニの雄が雌のフェロモンに反応する様子を水槽実験で観察した。雌の飼育水を雄の水槽に入れると、ウニの下に隠れていた雄のカニはウニの上に移動することが明らかとなった。
研究内容の(1)テッポウエビとハゼ共生関係の実態解明については、これまでの調査地である愛媛県愛南町に加え、佐渡島、舞鶴、西表島で行ったことで、大きな進展があった。餌環境が実際に泥場と砂地で異なるのかを調べた結果、佐渡島、舞鶴、西表島のいずれも漁港内や川の河口近くの泥場の方が、愛南町や西表沖合の砂地よりもベントス量が多いことが分かった。エビ4種ハゼ7種の行動解析の結果、餌量の異なる2地点ではエビとハゼの行動が大きく異なり、エビとハゼの共生関係の繋がりの強さが環境中の餌量の違いによって決まることが初めて示された。これら新規の結果によって、餌量仮説の証明に向けて大きく前進した。また、認知進化生態学研究としての、エビとハゼのコミュニケーションも明らかになってきており、今後の水槽実験に繋がる結果となっている。エビとハゼの餌量仮説についての研究成果は、現在、論文を執筆中である。
研究内容の(2)クマノミの宿主イソギンチャクに対する給餌行動の実態と種間関係に与える影響については、ほぼ結果が出揃い、現在投稿間近の状況である。これまでは愛媛県愛南町の個体群のみを扱ってきたが、沖縄やアメリカの研究者と連絡を取り合っており、2023年度の沖縄やパプアニューギニアでの研究に向けての準備を整えた。
研究内容の(3)ゼブラガニの雄による宿主ラッパウニの行動操作については、野外で採集してきたゼブラガニを用いて水槽実験を行った。まだ、予備的な実験に留まるが、2023年度のフェロモン分析、行動実験に向けて準備を進めることができた。
以上のように、2022年度はCOVID-19の影響を大きく受けることなく国内での野外調査が実施できたこともあり、共生の実態と維持機構、異種間の情報伝達機構を解明に向けて認知進化生態学的研究を予定通り進めることができた。このことから、概ね順調に研究が進んでいると判断される。
2023年度は、2022年度に引き続き(1)テッポウエビ-ハゼ、(2)クマノミ-イソギンチャクを相利共生系、(3)カニ-ウニの寄生系をモデルとして、認知進化生態学の視点から研究を進める。野外調査を中心に研究を行うが、認知については水槽実験を、フェロモン分析については実験室で生化学分析や行動実験を行う。
(1)2022年度の研究から、エビとハゼの共生関係の繋がりの強さが環境中の餌量の違いによって決まることが初めて示されたが、これまでの研究は種間比較(エビ4種ハゼ7種)であり、種の違いが行動の違いを生み出している可能性を排除できない。2023年度は、ベントス量が徐々に変化するような地点で同種のエビハゼペアを観察することで、餌量仮説を証明する。またエビの認知能力の高さを解明するため、テッポウエビの個体識別能力を水槽実験により調べる。さらに、巣内が見える水槽を用いて、巣内でのテッポウエビとハゼのコミュニケーションを明らかにする。
(2)クマノミの宿主イソギンチャクに対する給餌行動の実態については、学術雑誌へ発表する。執筆と並行して、野外調査を実施する。愛媛県愛南町に生息するクマノミは1種だけであるが、沖縄とパプアニューギニアには同所的にクマノミが数種生息している。クマノミの給餌行動がクマノミ属に広く見られること、さらに自分の宿主イソギンチャクとそうでない宿主とは、区別し、宿主選択的に給餌行動を行うことを検証する。また、これらの種組成の違いが、社会構造に大きく影響を与えている可能性が高く、クマノミとイソギンチャクの種間関係だけでなく、種内関係についても調査する。
(3)2023年度は、雄の行動を引き起こす未同定の匂い物質である雌フェロモンを同定する。雌の尿中の物質を各種クロマトグラフィーで分画し、フェロモン活性物質を室内行動実験で確認しながら単離し、NMRと質量分析で化学構造を決定する。 -
薄膜型酸素センサーを用いたアメフラシからの環境に優しいバイオフィルム抑制剤の探索
研究期間: 2020年04月 - 2023年03月 代表者: 神尾 道也
基盤研究(C) 研究代表者 20K06235
微生物の集合体であるバイオフィルムの付着は、船底、取水・浄水施設、水中観測装置等の施設機能低下の原因となる上、さらに有害な一部のフジツボや海藻等の着生も促進する。本研究は、海洋生物の中でも、特に発達した化学防御機構を持つアメフラシ類の皮膚から分泌されるバイオフィルム抑制物質を同定し、汚損防止剤開発に貢献する事を目的とする。バイオフィルム抑制試験法には、薬剤添加部位の呼吸量変動を記録する薄膜型酸素光化学センサー(Optode)を用いた新しい方法を確立し、致死的ではなく、より緩やかな抑制作用を持つ物質の探索方法を確立することで、環境に優しい汚損防止剤の探索に役立てる。
授業科目 【 表示 / 非表示 】
-
担当授業(学部)
フレッシュマンセミナー
-
化学Ⅱ
-
化学実験
-
化学概論Ⅱ
-
化学概論Ⅲ
-
環境生命化学Ⅱ
-
環境生命化学実験
-
担当授業(大学院)
有機構造解析
-
海洋環境科学特別演習
-
海洋環境科学特別研究